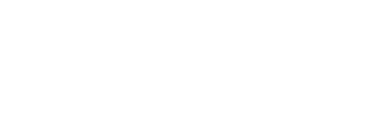「地域住民の認知症予防と従業員のWell-being向上」と題したワークショップにおいては,脳の健康維持増進を通じた地域住民の認知症予防と従業員のWell-being向上に関連する公共や民間サービスの連動について発表及び議論した.
これまで,脳構造を計測するMRI装置を用いた,脳の健康指標であるBHQ(Brain Healthcare Quotients,国際標準H.861)を通じて,多数の自治体や企業が認知症予防やWell-being向上を進めてきている.その中には公的サービスと民間サービスのオーバーラップがあり,異なるステークホルダー間をつなぐ有機的なエコシステム形成が産業発展の鍵といえる.
本セッションでは,京都大学國分先生よりBHQと認知機能やWell-beingとの関係性に関するこれまでの研究をご紹介頂いた.さらに,パナソニック難波室長より,MRIに基づいたBHQを発展させた表情からBHQを推定させるクイックBHQの開発成果及び,それを用いた自治体向けの認知症予防に向けた活動を報告頂いた.続いて,京都大学西垣先生から,民間企業内で用いた従業員向けの推定BHQの活用事例を公共機関利用との関連を踏まえて報告頂きました.これらの活動を横断する仕組みとしてノクターンキャピタルの岡本社長から,情報発信の事例でもあるノクターンテクノロジーレビューのご紹介を頂いた.最後に,山川から神戸大及びBHQ㈱と連携して作成した,自然な振る舞いの中からのBHQを推定するアルゴリズムの紹介と,その事例である絵画や仏像,さらには商品やサービス,空間の評価などに広がるエコシステム研究の可能性について発表した.
各発表後には,実際にクイックBHQを試して頂き,参加者の脳の健康状態を把握して頂くデモを体験頂いた.脳の年齢が良かった方はこれまで通りの活動を続けて頂ければよいという安堵がある一方で,残念ながら脳の年齢が実年齢より悪かった方々には,新たな脳を良くするサービスの必要性を強く感じて頂き,大変有意義なセッションになったと感じている.
脳の健康は,日本だけなく世界の課題であることからも,今後新たなサービスがうまれる先駆的な分野であると考えられる.一方で,健康サービス全般は,規制対応の煩雑さやエコシステム形成の複雑さ,またマネタイズの困難さと多くのハードルが存在している領域ともいえる.これらに対して,サービス学を通じた実証的なエコシステム研究を継続して推進していきたい.

著者
山川義徳
一般社団法人ブレインインパクト理事長,京都大学経営管理大学院特命教授,東京科学大学科学技術創成研究院特定教授,神戸大学産官学連携本部客員教授.国際標準に承認された脳の健康管理指標BHQを用いて,脳科学の非医療分野での産業化及び関連研究を推進.