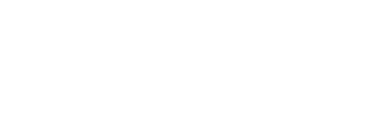村松 潤一, 戸谷 圭子(編著)
白桃書房, 200P, 2,545円+税, ISBN 9784561662518
「サービス経済化が進んでいる」「第三次産業が広がっている」—こんな言葉を耳にすることが増えました.でも,本書の序文では「サービスは第三次産業のことではない」と,少し意外な視点が提示されます.この一文を読んで,「えっ,どういうこと?」と驚く方もいれば,「ああ,あの話ね」とピンとくる方もいるかもしれません.
前者の方は,サービスを「無形の商品」として捉えているのではないでしょうか.一方,後者の方は,S-DロジックやSロジックで語られる「行為やプロセスとしてのサービス」(第1章)を思い出したのかもしれません.
本書では,この「行為やプロセスとしてのサービス」が社会全体に広がっている様子(第2章)を描きながら,受益者の生活世界,つまり文脈価値を中心に据えた,意欲的で挑戦的な研究が展開されています.たとえば,製造業のサービス化(第5章)や製品のIoT化などは,従来の「モノかサービスか」という分け方ではうまく説明できません.むしろ,サービスをプロセスとして捉え,価値を共に創るという視点(第3章)から見たほうが,現実の動きをより的確に理解できるのです.
また,S-Dロジックに馴染みのある方でも,「それは抽象的で,企業にとってどういう意味があるのか?」と疑問に思うかもしれません.本書では,価値は顧客(受益者)によって創られ,企業はその価値を促進するパートナーとして位置づけられています.そして,機能的な価値だけでなく,知識価値や感情価値といった新しい価値のかたちも,実証的に示されています(第3章).
こうした「サービス」の考え方は,社会のさまざまな分野に変化をもたらしています.たとえば,サービスの価値評価の方法(第4章),地域のエコシステムや活性化のあり方(第6章),教育のあり方(第7・8章)なども,「サービス駆動型」へとシフトしているのです.学問の世界でも,これまでの枠組みが見直され,再構築が求められています(第9章).
このように,本書は「モノからサービスへ」という大きなパラダイムシフトに対して,日本のサービス研究者が誠実に応えた一冊です.この挑戦の先には,「サービス学」という新しい学問の姿が見えてくるかもしれません.
今後は,「生活世界」や「制度(社会慣習)」,「生活の質」といったテーマをさらに深く掘り下げていくことで,本書の成果がより広がっていくことでしょう.
《菊池 一夫(明治大学 商学部 教授)》