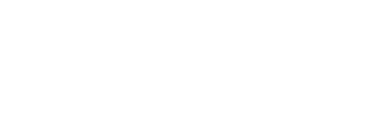本記事では,編集委員(三竹)が参加したセッションの中で,サービスのデザインと開発(2)を取り上げ,その詳細を示す.本大会では,「サービスのデザインと開発」をテーマとする口頭発表セッションは6つあり,合計18件の報告がなされた.そのうち,2日目に実施された「サービスのデザインと開発(2)」では以下に示す3件の報告がなされた.
報告概要
Web3の思想にもとづくサービスデザインツールの構築と評価
1件目の発表は,九州大学 徳久悟氏による講演であった.Web3とは,ブロックチェーン技術,分散化,トークンエコノミーなどの概念を取り入れた新たなWorld Wide Webのアイデアである.本研究は,Web3以前に開発されたサービスデザインツールをWeb3の世界観に適合するように再構築することを目的とする先駆的なものであった.具体的には,サービスコンセプトシート,コミュニティメンバージャーニーマップ,サービスエコシステムマップという3つのデザインツールを提案し,それらのツール群をサービスデザインのエキスパートへのインタビューを通して具体化を行なっている.筆者が本研究において興味深く感じたのは,Service dominant logic (SDL)におけるサービスエコシステムの原理をツールに明示的に反映しようとする点である.ミクロからマクロレベルまで,また,Institutionの概念など複雑なサービスシステムを表現するための体系的なツールは,確かに未だ存在しない.今後の更なるツールの精緻化とそれに関する続報を期待したい.
サービスLADの提案:大規模言語モデルと協働した優れたサービスづくりと組織づくり
サービス工学における設計(デザイン)アプローチは,社会的トレンドの変化や技術の発展に伴い,その様相を変化させてきた.2件目の発表は,現代におけるサービス工学のあり方の一つを提示するものであった.東京大学の原辰徳氏らは,近年著しく発展する大規模言語モデル(Large Language Model : LLM)と協働する新たなサービス設計計算機環境「サービスLAD(LLM-aided design)」を提唱した.本コンセプトの重要な点は,サービスデザインの各プロセスにおける個別的なLLMの活用ではなく,原らが開発に携わった規格ISO/TS 24082 (JIS Y 24082)「エクセレントサービスの設計」に基づき,その専門知識と設計プロセスをLLMに組み込み,整備したことだ.本発表のディスカッションにおいては,サービスデザインに生成AI(Artificial intelligent, 人工知能)を活用する本質的な意味,AIのハルシネーションとデザインの確からしさ,本アプローチが普及した際のエネルギー使用にかかる問題など様々な視点から議題が交わされており,本トピックに関する注目と盛り上がりを示していた.
創造するデザインを駆動する「描く」という方法
3件目は,公立はこだて未来大学の須永剛司氏らによよる,製造業の知識伝承を駆動するためのデザインアプローチに関する研究発表が行われた.須永らは,デザインの意味は,技術(例えば,AI)と現場の実践の間に「橋を架ける」ことだとし,その橋架けは,技術利用の文脈(コンテキスト)づくりだと主張する.そして,そのコンテキストづくりのために「描く」というデザインの中心的営みがいかに製造現場における知識の理解に寄与するかを検証した.近年,工学分野では製造現場におけるエキスパートの知識構造化,それとAIを組み合わせることによる現場支援に関する研究は多数報告されているが,形式化しきれない部分(コンテキスト)は削ぎ落とされてしまいがちである.本研究は,そこに着目し,実践者が自身の実践知に気づき,表現できることを支援する独自の視点が興味深い.本研究のようなデザイン学アプローチと上記の工学アプローチの間にも橋を架けることにも,期待したくなる研究発表であった.
おわりに
サービスデザインや設計の研究を取り巻く社会状況や技術動向は近年,目紛しく変化し続けている.本セッションで報告された発表はどれも,生成AIやWeb 3.0などの新たな技術・概念の登場に伴う,サービスデザイン再構成の必要性を認識し,それに取り組む挑戦的な研究であり,筆者自身とても刺激的なセッションであった.技術革新が日進月歩の現代において,新たなサービスデザインを規定することは難しい.しかし,将来の創造活動においてヒトとAIなどの新技術が協働するための様々な指針が確かに提示され始めており,今後の大会における継続的な報告が待ち望ましい.
著者
三竹祐矢
東京大学人工物工学研究センター 助教.東京都立大学大学院修了後、2023年4月より現職.サービス工学,ライフサイクル工学の研究に従事.